明日はいよいよ宅建試験ですね。
カフェでテキストを開きながら、最後の復習をしている人も多いと思います。
そんな中で、「全然覚えきれてない」「過去問も中途半端…」と焦っている人も、きっといるはずです。
実は、去年の自分もまさにそうでした。
🌀「受ける意味あるのかな」と思いながら始まった勉強
正直に言うと、宅建を受けようと思った動機はかなり薄かったです。
建築学科の授業で「不動産も勉強しておくといいよ」と言われたのがきっかけ。
「なんか就活に役立つかもな〜」くらいの軽い気持ちでした。
だから、最初の頃は勉強もかなり雑でした。
テキストを開いても眠くなるし、「法令上の制限?なにそれ?」状態。
それでも、なんとなく「やるって言っちゃったし」と思いながら続けていました。
📘 勉強量は少なくても、“流れ”をつかんだら見える世界が変わる
勉強を進めていく中で気づいたのは、
「全部を完璧に覚えようとするより、全体の地図を持つことが大事」ということです。
最初は「権利関係」も「宅建業法」もバラバラに見えるけど、
問題を解いていくうちに少しずつ線がつながっていく。
たとえば、
- 契約の流れを理解したら「宅建業法」も覚えやすくなる
- 建築基準法の感覚があれば「法令上の制限」も意外と入ってくる
こういう“橋渡し”を見つけた瞬間、勉強が楽しくなりました。
☕ 模試で落ち込んでも大丈夫。試験本番は「冷静さ」が勝つ
正直、模試は受けたことなかったし、過去問がボロボロの時もありました。
「これ、本番で受かる人なのか?」って不安しかなかったです。
でも本番当日、試験会場で周りの人の真剣な顔を見たとき、
「どうせなら自分も最後までやってみよう」と不思議と開き直れました。
そして試験中は、
「わかる問題を確実に取る」
それだけを意識しました。
難しい問題に時間を取られず、迷ったらマークして次へ。
終わってみたら、「思ってたよりできたかも?」という感覚。
結果41点で合格できました。
🌱 「完璧にやらなくても受かる」を伝えたい理由
宅建の勉強を通して感じたのは、
「頑張り方は人それぞれでいい」ということです。
SNSを見ると、「過去問10周」「300時間勉強しました!」みたいな人がたくさんいます。
でも実際、そうじゃなくても合格できます。
重要なのは、
- 苦手分野から逃げずに一度は向き合う
- 分からないことを「調べて理解しよう」とする
- 直前期に“とにかく手を動かす”
この3つさえできれば、十分戦えます。
🔑 建築学生としての視点から
建築を学んでいると、宅建の内容が“抽象的”に感じることがあります。
でも実は、建築と不動産は地続きなんです。
建物が建つ場所には必ず「土地のルール」があるし、
その土地には「人の生活」や「価値の流れ」がある。
宅建は、そうした“見えない基盤”を知るための第一歩です。
だから、もし今「自分なんかが受かるのかな」と思っている人がいたら、
自信を持って言いたいです。
建築を学ぶあなたなら、
きっと“まち”や“空間”を読む力で、法律の世界もちゃんと理解できます。
🌤️ 最後に
前日の夜に詰め込みすぎなくて大丈夫。
明日は**「知っていることを落ち着いて出す」**だけです。
睡眠をしっかり取って、
朝は少し早めに出て、会場の空気に慣れておく。
それだけで本番の集中力は全然違います。
✨建築学生からのエール
「完璧じゃなかった自分でも受かった」
だから、あなたも絶対に大丈夫です。
勉強してきた時間も、悩んだ日も、すべてが力になっています。
明日はその努力を信じて、
ゆっくり深呼吸して、問題冊子を開いてください。
応援しています📚🌿

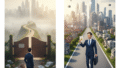
コメント