〜建築士と宅建士の報酬構造を比べて見えてくる現実〜
はじめに:教授のひとこと
ある建築学科の教授がこう言いました。
「建築士が材料費などを引いたらわずかしか残らないのに、宅建士はそれと同じくらいの報酬をもらっている。あいつらセコイわー。」
この発言、冗談のようでいて、業界構造をよく表しています。
建築士と宅建士、どちらも社会に欠かせない資格ですが、報酬の構造がまったく違うのです。
では、具体的にどれくらい違うのでしょうか?
仮定
- 宅建(仲介)手数料の計算式は、売買価格が高額(400万円超)の場合、原則として (売買価格 × 3%)+60,000円(上限)を用いる。
- 建築(建物)に関する数値は分かりやすくするため簡易にモデル化:
- 建物工事費の内訳は概ね 材料 65% / 労務 25% / 工事会社の粗利・諸経費(残り) 10% と仮定。
- 建築士(設計・監理)への報酬は建物工事費の 約10%(設計監理料の中間的な想定)とする。
- 建築士事務所の内部経費(事務所経費、人件費等)を差し引いた実質的な手取りは報酬の約40%程度と仮定(事務所規模で変動)。
例①:土地3,000万円+建物2,500万円のケース
例①(中規模ケース)
- 土地価格:3,000万円(30,000,000円)
- 建物工事費:2,500万円(25,000,000円)
- 合計:5,500万円(55,000,000円)
宅建(仲介)手数料
- 計算:55,000,000 × 3% + 60,000 = 1,710,000円(約171万円)
建築(建物)関連の数値
- 建物に対する設計監理料(仮に10%とする):25,000,000 × 10% = 2,500,000円(約250万円)
- ただし建築士事務所の内部経費等を仮に差し引くと、**実質的な手取り(設計者本人・事務所に残る額)**は:
- 2,500,000 × 40% ≒ 1,000,000円(約100万円)
- 同時に建物工事費の内訳(仮定)
- 材料:25,000,000 × 65% = 16,250,000円(約1625万円)
- 労務:25,000,000 × 25% = 6,250,000円(約625万円)
- 工事会社の粗利・諸経費(残り):2,500,000円(約250万円)
まとめ(例①)
- 宅建(仲介)手数料:約171万円(仲介会社・担当の取り分はここからさらに配分)
- 建築士への名目報酬:約250万円 → 実際の事務所手取りを仮定すると 約100万円
- 工事会社の粗利(建物全体に対する会社側の取り分):約250万円
この例だと、名目上は「建築士の報酬(250万円)>宅建手数料(171万円)」ですが、建築士の報酬は事務所経費・人件費で大きく削られ、実質手取りは宅建の担当者の取り分(仲介報酬の担当個人に回る割合)と同等か下回る可能性があります。一方、仲介手数料は成功報酬であり、営業費用や事務所配分はあるものの「案件1件でまとまった現金が動く」ため、個人レベルの取り分が大きく見えやすいのです。
| 項目 | 内容 | 計算 | 名目報酬額 | 実際の手取り(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 土地仲介(宅建士) | 仲介手数料(上限) | 5,500万円 × 3% + 6万円 | 約171万円 | 約80〜120万円(会社配分後) |
| 建築士 | 設計監理料(建物工事費の10%) | 2,500万円 × 10% | 約250万円 | 約100万円(事務所経費差引後) |
| 工務店(参考) | 工事会社の粗利部分 | 建物工事費の約10% | 約250万円 | 約200万円前後(経費差引前) |
※工事費のうち約65%が材料費、25%が労務費と仮定。
▶ 数字で見える“違い”
- 宅建士の仲介手数料は成功報酬で、1件成約すれば100万円前後の収入になるケースもあります。
- 一方、建築士は設計・監理で何か月も関わりながら、経費を差し引くと実質100万円前後しか残らないことも。
- 教授が言う「セコイ」という言葉は、こうした**“手間のわりに宅建士がもらいすぎに見える構造”**への皮肉なのです。
例②:土地5,000万円+建物4,000万円のケース
例②(大規模ケース)
- 土地価格:5,000万円(50,000,000円)
- 建物工事費:4,000万円(40,000,000円)
- 合計:9,000万円(90,000,000円)
宅建(仲介)手数料
- 計算:90,000,000 × 3% + 60,000 = 2,760,000円(約276万円)
建築(建物)関連の数値
- 設計監理料(10%想定):40,000,000 × 10% = 4,000,000円(約400万円)
- 建築士事務所の実質的手取り(40%仮定):4,000,000 × 40% = 1,600,000円(約160万円)
- 建物工事費内訳(仮定)
- 材料:40,000,000 × 65% = 26,000,000円(約2600万円)
- 労務:40,000,000 × 25% = 10,000,000円(約1000万円)
- 工事会社粗利等:4,000,000円(約400万円)
まとめ(例②)
- 宅建(仲介)手数料:約276万円
- 建築士の名目報酬:約400万円 → 実質手取りは 約160万円
- 工事会社の粗利:約400万円
この規模でも同様に、仲介手数料の名目額と比べて、建築側の「実際に手元に残る金額」は必ずしも大きくないことがわかります。
| 項目 | 内容 | 計算 | 名目報酬額 | 実際の手取り(概算) |
|---|---|---|---|---|
| 土地仲介(宅建士) | 仲介手数料(上限) | 9,000万円 × 3% + 6万円 | 約276万円 | 約130〜180万円(会社配分後) |
| 建築士 | 設計監理料(建物工事費の10%) | 4,000万円 × 10% | 約400万円 | 約160万円(事務所経費差引後) |
| 工務店(参考) | 工事会社の粗利部分 | 建物工事費の約10% | 約400万円 | 約300万円前後(経費差引前) |
▶ 教授の言葉に込められた本音
建築士は数か月、時には1年近くかけて設計・監理に取り組みます。
責任も重く、ミスがあれば数百万円の損害に直結することもあります。
一方、宅建士は取引をまとめた瞬間に報酬が確定します。
このように、
- 労働量や責任の重さは建築士の方が大きいのに、
- 実際に残る報酬額が宅建士と大差ない
という現実を教授は「セコイ」と表現したのです。
報酬構造の本質:名目よりも“残るお金”
| 観点 | 建築士 | 宅建士 |
|---|---|---|
| 報酬の性質 | 設計・監理料(成果報酬+責任伴う) | 仲介手数料(成功報酬) |
| 報酬の上限 | 特に法定なし(相場8〜12%) | 法定上限あり(3%+6万円) |
| 経費負担 | 高い(人件費・設備費・保険など) | 低め(営業費・広告費程度) |
| 責任の重さ | 高(設計・監理に法的責任) | 中(重要事項説明・契約責任) |
| 実質の残り額 | 名目の40%前後 | 名目の50〜70%前後 |
こうして並べると、
教授の「セコイ」という一言は金額の多寡ではなく、“報酬の中身”の違いを指していることが見えてきます。
まとめ:セコイ=ズルいではなく、「構造が軽い」
ここでいう“セコイ”とは「ずるい」ではなく、「構造的に軽い」という意味に近いのです。
建築士は、社会的価値を形にする仕事。
宅建士は、その価値を流通させる仕事。
どちらも欠かせない職能ですが、
報酬の構造を見ると、建築士がどれほど責任に比して報われにくい立場かが見えてきます。
教授の「セコイ」発言が意味していること(数字から読み取れる本質)
- 名目と実質の差
- 建築関係者が「受け取る報酬」として見せる金額(設計報酬や工事費の中の数値)は確かに大きい場合があるが、そこから材料費・下請け費用・事務所経費・長期的責任などを差し引くと、個人や事務所の“取り分”は意外に小さい。
- 一方で、宅建(仲介)の成功報酬は一括でまとまって入り、営業担当や仲介会社に回る“現金額”が目立ちやすい。
- 労働の性質の違い
- 建築の仕事は長期的で責任も大きく、成果(建物)は数十年残る。短期の“成果物”で一気に稼ぐ構造ではない。
- 宅建士(仲介)は取引の「成立」自体が報酬発生のトリガーで、一定の数をさばけばまとまった収入になる。
- 教授の論点は「公平感」
- 教授は「同等の金額が動いているが、建築にかかるコスト構造(材料・下請け・長期責任)を考えると、建築側の正当な取り分は相対的に小さい。なのに宅建側が簡単に(=手間のわりに)似たような額を得ているように見えるから“セコイ”と言った」──という観察をしている可能性が高いです。
結び
教授の「セコイ」という一言は刺激的ですが、本質は「名目上の金額」と「実際に残るお金・負う責任」が違う、という指摘です。報酬の“額”だけを比べると誤解が生まれますが、収入の構造やリスク負担を含めて見ると、職種ごとの違いがはっきりします。読者の皆さんも、職業や資格の価値を語るときは「名目額」だけでなく「実質」「継続性」「責任の重さ」を合わせて考えてみてください。
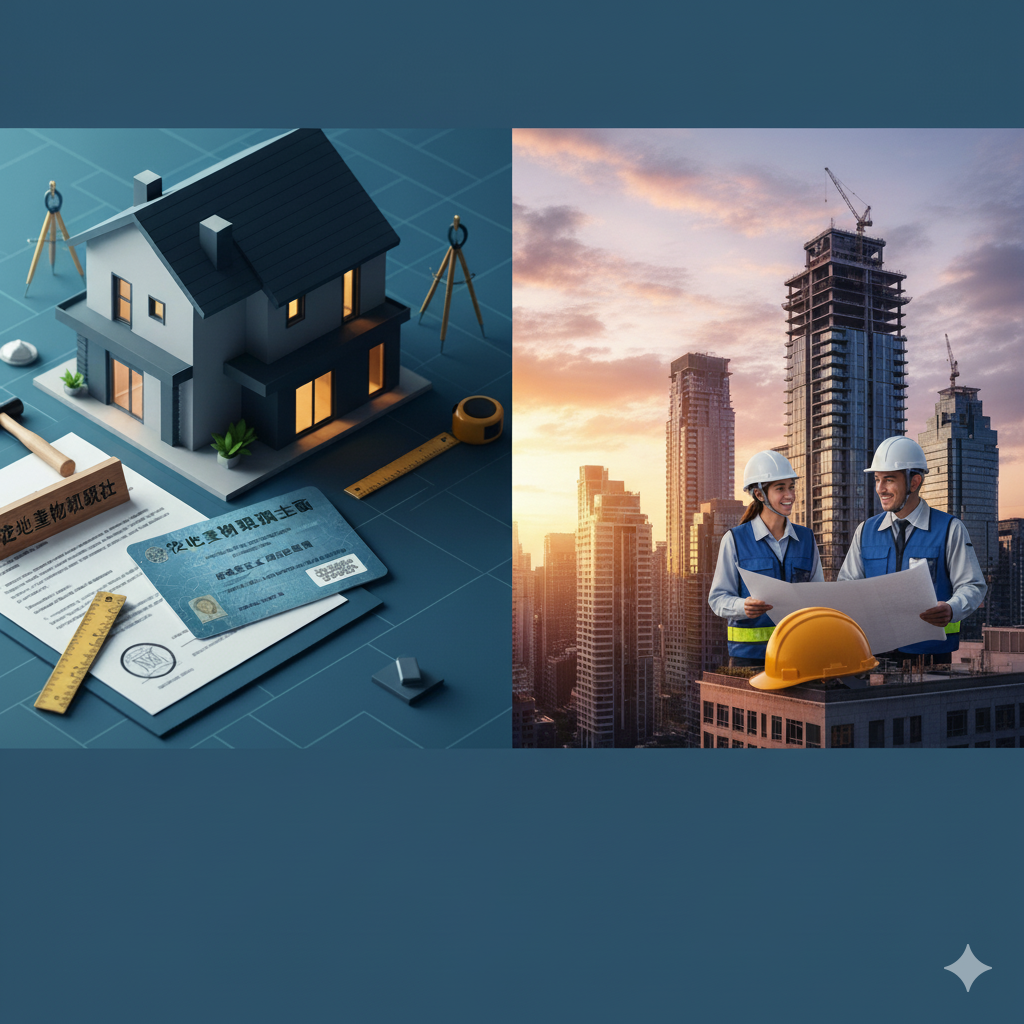
コメント