〜建築的条件+資産性+リスクを読み解く〜
建築学科で「敷地条件」と聞くと、日照や風向き、道路の位置など物理的な条件を思い浮かべる人が多いと思います。
でも、社会に出て設計をすると、それだけでは“いい土地”とは言えません。
実際に建てる前には、法規・資産性・災害リスク・市場価値など、複数のレイヤーを読み解く必要があります。
この回では、そんな「多層的な土地の見方」を学びます。
🌏 1. 建築的に“良い土地”が、必ずしも“安全”とは限らない
たとえば、南向きで日当たり抜群、駅からも近い土地。
図面上では理想的ですが、液状化地域だったり、洪水ハザードマップで真っ赤なエリアの可能性もあります。
「こんな条件、授業で聞いたことない!」という学生も多いでしょう。
でも、実務では**“安全”も含めて設計条件**なんです。
建築基準法や宅建業法では、
- 地盤の状態
- 宅地造成の履歴
- 災害リスク情報の開示
が義務づけられています。
つまり設計以前に「この土地で建てていいか?」を見抜く力が必要です。
💰 2. 資産性の視点を持つ
「この土地、設計的には面白いけど、売れない土地かも…」
そんなことを感じたことはありますか?
例えば旗竿地(奥まった形状の土地)はプランの工夫次第で魅力的にできますが、
市場では評価が低くなりやすいです。
建築の学生は“設計できるか”ばかり考えがちですが、
社会では“誰が買うか・住むか・維持できるか”まで見据える視点が重要です。
資産性は「未来の使われ方」に直結します。
つまり、設計者も不動産の目線で考える必要があるのです。
⚖️ 3. 法規と地形を読むスキル
土地を評価する上で避けて通れないのが法規制の層です。
たとえば:
- 用途地域
- 建ぺい率・容積率
- 道路との接道義務(建築基準法第42条)
これらを満たしていなければ、そもそも建てられません。
学生あるあるですが、「法規は製図試験のための暗記科目」と思っていませんか?
でも、実務では土地を選ぶ段階から法規を読むんです。
たとえば接道が2m未満の土地は再建築不可。
設計者がこの条件を見逃すと、計画自体が“法律違反”になります。
🌪️ 4. 災害リスクと地域性
東日本大震災や令和の豪雨以降、地形や地歴を読み解くことが重要視されています。
かつて川だった場所、盛土で造成された宅地、斜面地などは、
見た目ではわからないリスクの層を持っています。
宅建士は取引時に「水害リスク説明義務」を負いますが、
設計者も「防災設計」の観点から同じ視点を持つべきです。
つまり、
“建てるための土地を見る”から、“暮らしを守る土地を見る”へ。
🧭 5. まとめ
これからの建築学生に求められるのは、
「形のデザイン」だけでなく「土地の背景を読む力」です。
地盤・災害・法規・資産性・歴史。
これらを一枚のレイヤーとして扱える人こそが、
“土地の価値を設計できる建築家”です。
📍土地を読む力=社会を読む力。
次の回では、その「法規と不動産の交点」をさらに掘り下げます。

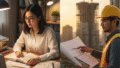
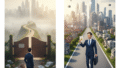
コメント