はじめに
宅建試験では、全50問のうち建築基準法から2〜3問が出題されます。
数は少ないですが、毎年ほぼ必ず出題される重要分野です。
この記事では、建築学生にもわかりやすいように、
「建築基準法 × 宅建試験」の出題範囲を図と表で整理して解説します。
────────────────────
プロフィール
建築学科の大学生
「学生証だけじゃつまらない、人と違う身分証明書が欲しい」
そんな理由で宅建を取りました。
建築と不動産、法律や土地のことを知る中で、モノの見え方が少し変わった気がします。
このブログでは、建築学生として宅建を学んだ経験や考えたことを、ゆるく発信していきます。
────────────────────
🏙 建築基準法の全体構造
まずは全体像をざっくりつかみましょう👇
建築基準法の目的:
「国民の生命・健康・財産の保護」と「公共の福祉の増進」
├ 第1章 総則(定義など)
├ 第2章 建築物の敷地・構造・設備・用途に関する規定
│ ├ 敷地・構造・設備の基準(接道義務など)
│ ├ 用途制限(用途地域ごとの建物制限)
│ ├ 建ぺい率・容積率・高さ制限
│ └ 防火・避難・採光など
├ 第3章 建築物の建築手続き(確認申請など)
├ 第4章 建築審査会
└ 第5章 罰則
宅建で出るのはこの中でも👇
- 第2章(建築物の制限関係)
- 第3章(建築確認)
に集中しています。
📗 宅建で出る建築基準法の分野と頻出ポイント
| 分野 | 出題頻度 | 内容 | 覚えるコツ |
|---|---|---|---|
| ① 用途地域による建築制限 | ★★★★★ | どの地域にどんな建物が建てられるか | 「住居系=静か、商業系=にぎやか」で整理 |
| ② 建ぺい率・容積率 | ★★★★★ | 敷地面積に対する建築面積・延床面積の制限 | 「数字の意味」を図で覚える |
| ③ 接道義務 | ★★★★☆ | 幅員4m以上の道路に2m以上接する | 「建てられない土地」を見分ける感覚 |
| ④ 高さ・日影制限 | ★★★☆☆ | 低層住居地域などでの高さ制限 | 「高さ=日照環境を守るため」と理解 |
| ⑤ 防火地域・準防火地域 | ★★★☆☆ | 耐火・準耐火建築物の義務 | 用途地域とセットで暗記 |
| ⑥ 建築確認・検査済証 | ★★★★☆ | 建築する前に許可が必要 | 「確認→着工→完了」の流れで整理 |
🧱 図で理解する建ぺい率と容積率
1. 建ぺい率(建築面積 ÷ 敷地面積)
敷地の何%まで建物を建てていいか
┌──────────────┐
│■■■■■建築面積■■■■■│ ← 建ぺい率 = 60%なら敷地の6割までOK
└──────────────┘
💡ポイント
- 建ぺい率 = 建物の「広がり」を制限する
- 例:敷地100㎡、建ぺい率60% → 建築面積は最大60㎡まで
2. 容積率(延べ床面積 ÷ 敷地面積)
敷地に対して建物を何階まで積めるか
↑
┌───────────┐ 3階:延べ床30㎡
│■■■■■■■■■■■■■│
│■■■■■■■■■■■■■│ 2階:延べ床30㎡
│■■■■■■■■■■■■■│ 1階:延べ床30㎡
└───────────┘
敷地:100㎡
💡ポイント
- 容積率 = 建物の「高さ方向のボリューム」
- 例:敷地100㎡、容積率200% → 延べ床200㎡まで
🏘 用途地域の分類を図で覚える
──────────────────────────
住宅系地域(静か・暮らし中心)
──────────────────────────
第1種低層住居専用地域 … 低層住宅だけ
第2種低層住居専用地域 … 小規模店舗OK
第1種中高層住居専用地域 … マンション中心
第2種中高層住居専用地域 … 商業施設も可
第1種住居地域 … 生活関連施設もOK
第2種住居地域 … 小規模店舗・事務所OK
──────────────────────────
商業系地域(にぎやか)
──────────────────────────
近隣商業地域 … 住宅と商業が混在
商業地域 … 百貨店・オフィスビルなど可
──────────────────────────
工業系地域(ものづくり中心)
──────────────────────────
準工業地域 … 住宅も一部可
工業地域 … 工場OK・住宅NGあり
工業専用地域 … 住宅NG
──────────────────────────
💡ポイント
- 「静かな住宅地ほど建物制限が厳しい」
- 「商業・工業系になるほど自由度が高い」
🛣 接道義務の図解
道路に接していない土地では原則建築不可!
建築可能
┌──────────────┐
│建物│ 道路(4m以上) │
└──┬──────────┘
↑ 接道2m以上が必要
建築不可(接道不足)
┌──────────────┐
│建物│←1mしか接していない
└──┬──────────┘
💡ポイント
接道義務:
建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない。
🔥 防火地域・準防火地域
| 地域 | 主な制限 | 対応する建築物 |
|---|---|---|
| 防火地域 | 火災の危険が特に大きい場所 | 耐火建築物のみ可 |
| 準防火地域 | 火災の危険が比較的高い場所 | 準耐火建築物OK(木造でも条件付) |
💡都市中心部や駅前は「防火地域」に指定されることが多い。
✅ 建築確認と検査の流れ
① 建築計画(設計完了)
↓
② 建築確認申請
↓
③ 確認済証が交付されてから着工
↓
④ 工事完了後、完了検査
↓
⑤ 検査済証の交付(ここで建物が“法的に完成”)
💡ポイント
「確認済証がない建築」は違法建築になる。
宅建でも、未検査建物の取引時には注意が必要。
🧩 まとめ:宅建で学ぶ建築基準法は“設計の基礎”
| 学ぶ視点 | 宅建での意味 | 建築での活用 |
|---|---|---|
| 用途地域 | 建築可能な用途の判定 | 設計コンセプト設定 |
| 建ぺい率・容積率 | 数字で建築制限を理解 | 敷地に合う規模計画 |
| 接道義務 | 建築可否の判断 | 敷地調査・配置計画 |
| 防火地域 | 構造の選定 | 耐火・防火設計 |
| 建築確認 | 手続きの理解 | 実務への橋渡し |
💬 最後に
宅建で扱う建築基準法は、「試験用の暗記」ではなく、
実務で役立つ“敷地・法規の思考法”を学ぶ機会です。
設計・都市計画・不動産開発のどの分野に進むとしても、
建築基準法の理解なしに建築は語れません。
宅建を通して、
「法を読む力」×「設計する力」=本当の建築的思考
を身につけていきましょう。

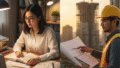
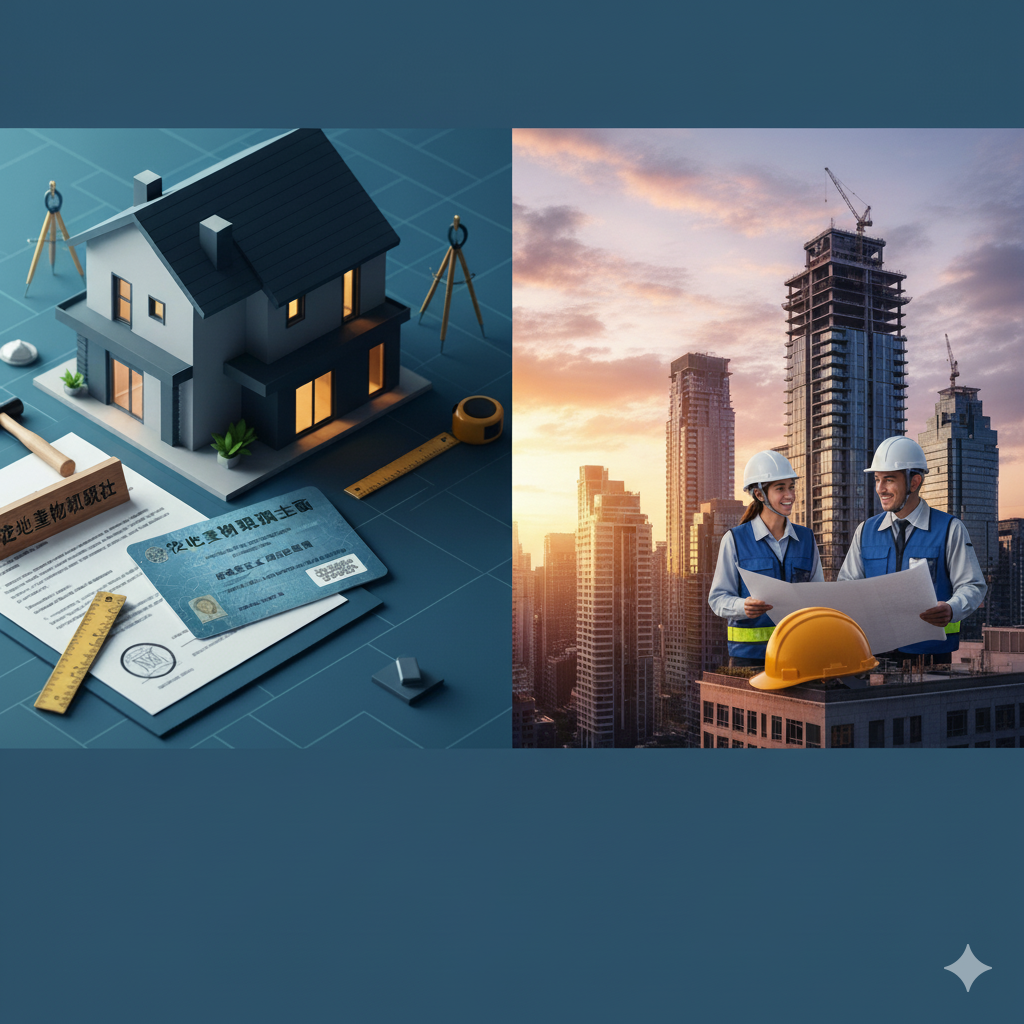
コメント