〜建築と不動産をつなぐ“見えない境界線”〜
🏗️ 1. 建築確認と登記・取引の接点
建築学生の多くが混乱するのが、「建築確認」と「登記」の違いです。
設計図を描いて役所に確認申請を出すのが建築確認。
一方、完成後にその建物を法的に記録するのが登記。
ここで意外と見落とされがちなのが、
確認申請が通っても、登記できるとは限らないという点。
たとえば接道義務を満たしていない建物は、
確認は下りても将来の取引で“再建築不可”とされる場合があります。
つまり、法的な整合性を意識して設計しなければ、
「建てたけど売れない建物」を生んでしまうリスクがあるのです。
📏 2. 道路と接道のリアル
宅建でも頻出するのが**道路の種類(42条1項・2項道路)**です。
建築基準法上の“道路”は、実際の地図上の“道路”とは違うことが多い。
学生の「あるある」ですが、
「え、この小道も道路扱いになるの?」
「市道なのに建築できないの?」
と驚く人が多いです。
これは、都市計画や区画整理など、行政上の履歴が複雑に絡むから。
設計段階で現地調査+法規確認を怠ると、後で取り返しがつきません。
📐 3. 容積率と取引価値の関係
設計課題で容積率を“数字遊び”のように扱う人もいますが、
実務ではこれは土地の値段に直結する数値です。
例えば容積率200%の土地より、300%の土地は単純に「より多く建てられる=価値が高い」。
この構造を理解しているだけで、土地を見る目が変わります。
📊 建築的制約=経済的ポテンシャル
この感覚を学生のうちに持つと、社会で一歩先に進めます。
🏠 4. 建築確認と宅建の接点図
土地調査 → 法規チェック → 建築計画 → 確認申請 → 建築 → 登記 → 取引
この流れのどこに関わるかで、
建築士・宅建士・行政・施主の立場が変わります。
学生のうちは「設計図提出で終わり」ですが、
実務ではその先に**“法と市場をまたぐプロセス”**があります。
🧭 5. まとめ
建築と不動産を分けて考える時代は終わりました。
これからの設計者は、**法のつながりを理解する“通訳者”**のような存在です。
建築基準法の数字も、宅建法の条文も、
「建てる」「住む」「売る」「守る」を一続きにするための道具。
📘 法を読む力=建築を社会につなぐ力。
次回は、この延長線上で“建築学生のキャリアと不動産脳”を考えます。

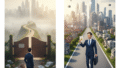
コメント