― 建築×宅建の“生活感覚”で考える設計 ―
こんにちは!今回は、建築学生が意外と苦手にしがちなテーマ、
**「人の暮らし」**を設計にどう反映させるか、というお話です。
設計課題をやっていると、模型や図面の完成度ばかりに意識が向いてしまい、
“人がどう暮らすか”という最も根本的な視点を忘れてしまうこと、ありませんか?
実はその「暮らし」を読み解く力、
宅建(宅地建物取引士)の知識があると驚くほど深まります💡
🧭 1. 「人の暮らし」をデザインするとは?
設計課題では「家族構成:夫婦+子ども2人」みたいな設定がよくありますよね。
でも、それをただ条件として処理していませんか?
実際の設計では、
- 子どもが成長したら部屋はどう使われる?
- 親が老いたとき、階段は負担にならない?
- 家族が家で一番長く過ごす場所はどこ?
こうした**“時間軸のある暮らし方”を考えることが求められます。
建築は“空間”をデザインする学問ですが、
本質的には“人の時間”をデザインする仕事**なんです。
ここで宅建の視点が効いてきます。
宅建では「借地借家法」「区分所有法」など、
家族の変化・所有・管理といった“生活の持続”を扱います。
つまり、宅建を学ぶことは、
人がどう住み続けるか=暮らしの変化を設計に取り込む訓練でもあるんです。
🏗️ 2. 授業で見落としがちな「生活スケール」
設計をしていて、こんな経験はありませんか?
「模型では美しいけど、実際に使うと狭い…」
「家具を置くスペースを忘れていた」
これは多くの建築学生が一度は通る“あるある”です。
建築学の授業ではミリ単位の図面を描く一方で、
“人のサイズ”を体で感じる機会が少ないのが現実です。
宅建の「住宅性能表示制度」や「建築確認」では、
部屋の広さ、採光、通風、バリアフリーなど、
実際に生活できる基準が数値で定められています。
この制度を理解すると、
「なぜこの寸法が必要なのか?」が腑に落ちてきます。
つまり、宅建を通じて**“人が快適に暮らすための設計寸法”**を知ることができるのです。
🌿 3. 暮らしの“リアル”は宅建に隠れている
宅建の勉強では、最初に「権利関係」や「契約」の話が出てきます。
一見、建築とは関係なさそうですよね。
でも、たとえば「賃貸契約」には人の生活のリアルが詰まっています。
- ペットを飼えるかどうか
- 日当たりが悪い部屋は人気が下がる
- 騒音や眺望の条件で家賃が変わる
これらは、人が空間をどう感じるか=設計の本質に直結しています。
つまり、宅建は“取引の学問”というよりも、
“人がどう暮らしを選ぶか”を学ぶ学問なんです。
住宅の「価値」を考えることは、
単に経済的な話ではなく、
**「この建築が人の生活にどう影響するか」**という視点を持つこと。
これは、設計課題ではなかなか教えてもらえない感覚です。
🪴 4. 「暮らしを設計に入れる」とはどういうこと?
人の暮らしを設計に取り込むとは、
単に家具を置くとか、生活動線を描くことではありません。
それは、“人がどう感じ、どう使うか”までを設計するということです。
たとえば:
- 南向きの大きな窓=明るいだけでなく「安心感」や「解放感」をつくる
- 道路に面した玄関=「通りとの関係性」や「防犯性」にも影響
- 廊下の幅=「家族がすれ違うときの距離感」までデザイン
つまり、建築は感情を設計する行為でもあります。
宅建で学ぶ用途地域も、ただの法規ではありません。
そこには「人がどんな環境で暮らしたいか」という都市の思想があるのです。
- 第一種低層住居専用地域 → 静かな生活を守る
- 商業地域 → 活気と交流を生み出す
用途地域を読むことは、“街の暮らし方を読む”ことなんです。
👣 5. 建築学生が陥りやすい“生活感のない建築”
設計を進めていて、よく先生に言われる言葉。
「この建築には人の気配がない」
模型やCGはきれいなのに、生活が感じられない。
これは、学生設計の典型的な課題です。
理由は簡単で、“人の行為”を図面に落とし込んでいないから。
💬 たとえば:
- 朝、通学前に家族が集まる場所はどこ?
- 雨の日、靴を乾かすスペースはある?
- 料理中、子どもの姿が見える?
こうしたリアルな生活の瞬間を想像することで、
図面の線が“人の物語”に変わります📖
🏘️ 6. 「暮らし」は建築と不動産の交差点にある
建築と不動産の関係を一言で言うなら、
「建築が形をつくり、不動産が暮らしを支える」。
設計者が宅建を理解することで、
- 建物の資産価値を考慮した設計ができる
- 管理・運用を意識した素材や配置を選べる
- 人が暮らしを継続できる建築をつくれる
つまり、宅建は「設計後の世界」を教えてくれる資格なんです。
建築だけを学んでいると、完成した瞬間がゴールに見えますが、
不動産の世界では、“使われ続ける建築”こそ本番です。
✨ 7. まとめ:暮らしを包む設計へ
建築は「形」をつくる仕事。
不動産は「暮らし」を守る仕事。
でも本当は、その2つは地続きです。
宅建を学ぶことで、
建築の“線”に人の“息づかい”を重ねることができます。
「いい建築」は、美しいだけでなく、使われ続ける建築。
「暮らしを考える建築」は、時間に耐えるデザインです。」
模型の中に人を置いて考えてみましょう。
朝の光、夜の静けさ、雨の日の匂い…。
それを想像できたとき、あなたの設計は本当の意味で建築になります。
📚 次回予告:第6回「不動産視点で見る“いい土地”“悪い土地”」
土地を見る目を鍛えることで、設計の深みが変わります。
建築学生が見落としがちな“敷地の裏側”を一緒に見ていきましょう🌏

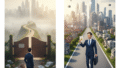
コメント