― 宅建と建築の“あいだ”にあるリアルな設計思考 ―
こんにちは!今回は、建築を学ぶうえで忘れがちなテーマ、
「人の暮らしを設計にどう取り込むか」 について考えていきます🌿
建築の授業では、どうしても「構造」「意匠」「法規」といった要素ごとに分けて学びますよね。
でも、実際の建築設計ではそのすべてが**“人の暮らし”を支えるために存在している**んです。
特に、宅建(宅地建物取引士)を学んでいるとわかるように、
建物は「商品」である前に、「人が生きる場所」。
この“あたりまえ”をどう設計に落とし込むかが、建築家の腕の見せどころなんです💡
👣 1.「人のスケール」を忘れた設計になっていませんか?
模型づくりに夢中になっていると、
つい “人間のサイズ感” を忘れてしまうこと、ありませんか?
- 廊下が細くてすれ違えない
- キッチンに立つと吊戸棚が高すぎて届かない
- 窓の位置が座ったときの目線とかみ合っていない
これ、設計学生あるあるです😂
でも、宅建の視点で見ると、これらは**「住み心地の悪さ=資産価値の低下」**に直結します。
つまり、人の動線や心理的な快適さを無視すると、
法律的にも経済的にも“よくない建築”になってしまうんです。
設計中は「この空間で誰が、どんな動きをするか?」を
1日の時間軸でシミュレーションすることが大切です。
朝、家を出る前の慌ただしい時間。
夜、帰ってきてほっとする時間。
そのとき、人はどんな姿勢で、どんな行動をしているのか。
この“暮らしのリズム”を空間に反映させることが、
**「人を中心にした建築」**への第一歩です。
🏡 2.宅建が教えてくれる「暮らしのリアル」
宅建の勉強をしていると、
借地借家法、区分所有法、住宅性能表示制度など、
一見「法律の世界」に思える内容がたくさん出てきます。
でも実は、これらの条文の背景には
**「人が安心して暮らすための仕組み」**が隠れています。
たとえば、
- 借家人が急に追い出されないようにする権利
- マンションでトラブルを防ぐための管理規約
- 建物の断熱・耐震性能を数値で示す制度
これらはすべて「人の生活を守るためのデザイン」なんです。
建築学生が見落としがちなのは、
“法規=制限”ではなく、“人を守る仕組み”だという視点。
宅建を学ぶと、建築を“暮らしの目線”から見直すことができます👀
🌇 3.図面の中に「生活のにおい」を入れよう
課題で図面を描くとき、気づくと**“きれいな線”**ばかり描いていませんか?
でも、実際の生活ってもっと雑然としていて、
カバンが置かれ、洗濯物が干され、玄関には傘が転がっている☂️
つまり、**暮らしとは「予定調和ではない動き」**の連続なんです。
だからこそ、
- 窓の位置は光だけでなく「風の通り」も考える
- 収納の配置は「ものの居場所」をデザインする
- 家具レイアウトを仮定して図面を描く
このように、図面に“人の気配”を入れると、空間がぐっと生きてきます。
「生活感」を恐れず、むしろ設計の素材として取り込む。
それが、人のための建築の第一歩です✨
🏙️ 4.“住まい”を超えて“暮らしの場”を考える
現代の建築では、住宅だけでなく、
コワーキングスペース、コミュニティハウス、複合施設など、
「暮らし」と「仕事」「地域」が混ざり合う空間が増えています。
このときに大切なのが、
“誰のための空間か”を明確にすること。
宅建でいう「用途地域」や「建ぺい率・容積率」は、
単に制限ではなく、地域の暮らし方を誘導するルールなんです。
たとえば、
- 第一種低層住居専用地域では“静かな生活”を守るための規制
- 近隣商業地域では“人が行き交うにぎわい”を促す設計が求められる
つまり、**建築は都市の中の“暮らしの単位”**なんです。
建築学生がこの視点を持つと、課題での“敷地分析”がぐっと深まります💡
💬 5.学生が陥りやすい「暮らしの想像力不足」
設計課題でよくある失敗が、
「見た目はかっこいいけど、人がどう使うか見えてこない」
というパターン。
私もかつて、模型を褒められたのに先生にこう言われました。
「この階段、朝の通勤時間に5人すれ違ったらどうなるの?」
ハッとしました。
その瞬間、**設計とは“絵”ではなく“行為のデザイン”**だと気づいたんです。
だから今は、どんな課題でも必ず
「ここで人が何をしているか」を一人ひとり想像するようにしています。
- このベンチに座る人はどんな気分?
- このキッチンで料理する人はどんな姿勢?
- この窓から見える景色で、どんな感情が生まれる?
そう考えると、設計図が**“人の物語”**に変わります📖
🌿 6.まとめ:暮らしをデザインする建築へ
建築は、単なる形づくりではありません。
「人の時間」と「空間」をどう重ねるかという提案です。
宅建が教えてくれるのは、
建築が“社会の中でどう機能するか”。
建築学が教えてくれるのは、
建築が“人の心にどう響くか”。
この2つをつなげることこそ、
これからの建築学生に求められる視点だと思います✨
💬 最後にひとこと
「いい建築」は、法規にも構造にもデザインにも優れている。
でも「人の暮らしを包みこむ建築」は、もっと深い。
模型の中に、図面の線の中に、
**“人の息づかい”**を感じる設計をしていきたいですね🌸

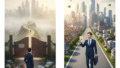
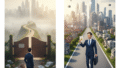
コメント